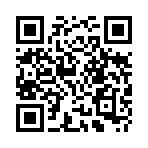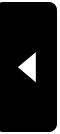2017年10月24日
ライトジギングロッドの穂先折れを修理してみた
友人が前回のLTアジで穂先を破損してしまったので、それを修理してみました。それほど高額なロッドではなかったのである意味練習には丁度良いという事で過去記事を参考にガイドをつなぎ直して修理。それほど難しくも無く強度的には結構うまくいったようなので記事にしてみたいと思います。

今回のロッドの折れ方は第二ガイドの先からポッキリです。LTアジ釣りでライトジギングロッドを代用したのですが、勢い良くしゃくったタイミングでポッキリと逝ってしまったようです。ロッドのマックスウェイトは120g。それに対して40号のビシは140gぐらいのはずなので、確かにウェイトオーバーといえばオーバーなのですが、20メートル前後の浅場でそれほど激しくビシをしゃくる必要もないので、普通は持ちこたえるような気がします。しゃくりすぎたのか、安いロッドが悪かったのかはわかりませんが、折れてしまったものは仕方がない。自己責任の結果として自分で修理する事に・・・あまり工作に自信がないということで、引き取って修理する事にしました。
参考に下のはこちらのブログ
SUPER BORA POWERS「そうなんよ、ロッド折れたんっすよ・・・orz」
折れ方がほぼ同じということで、同じ様に第2ガイドを諦めて、その部分にトップガイドをつける事にしました。
サイトの記事を参考に部材を調達。ガイドはそのまま流用し、ブランクスも今あるブランクスでどうにかするということで買い足すものは接着剤関係のみ。まずはアロンアルファ釣り名人
アロンアルファの中では硬化時の粘度が高いのが特徴のようです。硬化した時にパキッと割れない。実は釣り用のアロンアルファがある事今回初めて知りました。世の中色んなものがあるもんです。ついでにプラスチック用のアロンアルファも。使い分けは後ほど。
更にもう一つ追加したのが2液式のウレタン。
こちらはルアーやメタルジグの保護とかで良く見かけるもの。ルアーの保護にこれまでも使った事はありますが、メタルジグを酷使する程釣りに行かない事に気づき、それ以来それほど使った事はありません。割れたールアーを修理する為にたまに使う程度。それさえも最近はUVで硬化するレジンを使う事が多くなってきたので使うのは久々の気がします。
調達先はネットでも良かったのですが、ふと銀糸町キャスティングに出かけた時にすべて見つかったので購入。しかし、釣り具専門店のウレタンの種類は豊富ですね。ホームセンターではなかなか透明のウレタンが見つけ難いことがあるんですけど、釣具屋だとよりどりみどりで逆に選ぶのに困ります。調達が終わったら早速修理開始です。
まずはブランクスからガイドを取り外します。まずは第2ガイドをライターで軽く炙って取り外します。ちょっと炙るとすぐにトロッとウレタンが溶けるので、後はカッターで周りを削ると簡単にとれました。

折れた部分も綺麗な折れ口なので少し削れば良さそうです。
次にトップガイドを再利用する為に取り外す・・・が、これがうまくいかない。ブランクスが抜けません・・・うーん困った。ということで、いっそブランクスを燃やす事に。ブランクスというのはプラスチックと炭素繊維でできているので燃やすとぼろぼろになるはず。ということでペンチで挟んでライターで炙ります。おー燃える。少し冷ました後でブランクスを爪楊枝と針で穿り返すと綺麗に取れました。たぶん。

まあ穴の中に少し残ってるかもしれませんが、取りあえず装着に十分な深度は確保できたのでオッケー。素人の作業には多少の寛容な心が大事。
さてつぎは取り外したトップガイドを本体のブランクスに取り付けます。もちろん穂先の太さが違うので、そのままとりつけることはできません。参考にしたサイトによると折れたブランクスを削って本体のブランクスの穴に差し込んでいますが、今回はその穴がかなり小さく差し込むことができません。それ以前に燃やしちゃったしね。ということで、本体のブランクス自体を削って細くすることで差し込める様にします。カッターをつかってゴリゴリと削ります。結構硬い。あまり削りすぎると折れるので慎重に・・・おおよそトップガイドの穴の8割にはめ込めるようになったところで終了。

ちょっと危なっかしい状態ですが、このあと補強していけばどうにかなりそうな感じです。
さてこの状態でまずはブランクスの先にアロンアルファを塗ってトップガイドを取り付けます。この時のアロンアルファーは釣り用ではなく、プラスチック用を使用。これについては若干自信が無いんですが、ブランクスの成分はプラスチックを炭素繊維で強化したものと理解しているので、ガイドとブランクスの接地面自体はプラスチック用のアロンアルファについているポリマー(前処理剤)にて一度接着面を処理した方が強度が高いのではと考えました。ということで、ポリマーを綿棒で塗り塗りして少し時間をおきます。それからアロンアルファ本体で接着。あっというまに硬化。ちなみにこれはトップガイドだからって事もあって、中間のガイドだとブランクスに乗せてスレッド補修糸で接着するだけなので、曲がりに強いアロンアルファ釣り名人の方が良いんではないかと思います。
さて次はスレッド糸でブランクスとガイドを補強します。

巻き方はスレッド糸の商品自体に書いてある。

親切なパッケージでありがたい。補強の意味も込めてかなり広範囲に巻き巻き・・・3重に巻いて尖端を引っ張り込んで切断。

途中でちょっと巻き目が見えにくくなったので不格好になりましたが、強度的には問題ないということで続行。このスレッドを今度はアロンアルファ釣り名人で固めます。

こちらはスレッドとブランクス表面の伸縮を考慮して、柔らかい釣り名人を使用。巻いたスレッド全体に染み込ませて硬化させます。この時点でかなりの強度が出てきました。ここでさらにもう一手間。アロンアルファ釣り名人が乾いた上からウレタン系の硬化剤を塗ります。

2液式の硬化剤なので、一旦ペットボトルのキャップにストローで吸い上げて(口で吸うわけじゃ無いですよ。ズボッと漬けて反対の穴を親指で塞ぐだけ)2つの液を混合します。

若干硬化して粘土がでてきたところで綿棒で塗ります。あまり時間をおきすぎて、粘土が高くなりすぎると綿棒の糸くずがついてしまうので気をつけましょう。アロンアルファに比べると硬化速度はゆっくりなので焦らずにやれます。十分に塗ったら硬化を待ちます。半日は置いときましょう。

さて、ドキドキしながら曲げてみます。お~固まってる。曲げてもびくともしません。試しに天井へ・・・
きれいに曲がってます。表面にヒビもでてない。実釣してみないとわかりませんが、とりあえず成功の様です。さらにここで若干欲が。せっかくやりたい放題にできる竿なので、いっそ穂先を見やすいように色を付けてプチカスタマイズしてみることに。たまにルアーの着色に使っている蛍光オレンジのマニキュアでウレタンが硬化したところを塗ります。うーん、今思うとウレタンの前に塗ればよかった。まあ今さら遅いか。今度はそうしよう。。。ってな反省をしながら完成!

蛍光オレンジで穂先がぐっと見やすくなりました。再度天井での強度実験。

バッチリみたいです。
なんか夕マヅメアジとかメバル船とか乗りたくなっちゃう。そしたら更に蓄光塗料に塗り直したりしたくなっちゃったりして・・・。キャンプも釣りも新しいメンテナンスを覚えるのってたのしー!次はリールかなぁ。


■ライトジギングロッドの穂先折れを修理してみた 目次
準備の為に材料を揃える
今回のロッドの折れ方は第二ガイドの先からポッキリです。LTアジ釣りでライトジギングロッドを代用したのですが、勢い良くしゃくったタイミングでポッキリと逝ってしまったようです。ロッドのマックスウェイトは120g。それに対して40号のビシは140gぐらいのはずなので、確かにウェイトオーバーといえばオーバーなのですが、20メートル前後の浅場でそれほど激しくビシをしゃくる必要もないので、普通は持ちこたえるような気がします。しゃくりすぎたのか、安いロッドが悪かったのかはわかりませんが、折れてしまったものは仕方がない。自己責任の結果として自分で修理する事に・・・あまり工作に自信がないということで、引き取って修理する事にしました。
参考に下のはこちらのブログ
SUPER BORA POWERS「そうなんよ、ロッド折れたんっすよ・・・orz」
折れ方がほぼ同じということで、同じ様に第2ガイドを諦めて、その部分にトップガイドをつける事にしました。
サイトの記事を参考に部材を調達。ガイドはそのまま流用し、ブランクスも今あるブランクスでどうにかするということで買い足すものは接着剤関係のみ。まずはアロンアルファ釣り名人
アロンアルファの中では硬化時の粘度が高いのが特徴のようです。硬化した時にパキッと割れない。実は釣り用のアロンアルファがある事今回初めて知りました。世の中色んなものがあるもんです。ついでにプラスチック用のアロンアルファも。使い分けは後ほど。
更にもう一つ追加したのが2液式のウレタン。
こちらはルアーやメタルジグの保護とかで良く見かけるもの。ルアーの保護にこれまでも使った事はありますが、メタルジグを酷使する程釣りに行かない事に気づき、それ以来それほど使った事はありません。割れたールアーを修理する為にたまに使う程度。それさえも最近はUVで硬化するレジンを使う事が多くなってきたので使うのは久々の気がします。
調達先はネットでも良かったのですが、ふと銀糸町キャスティングに出かけた時にすべて見つかったので購入。しかし、釣り具専門店のウレタンの種類は豊富ですね。ホームセンターではなかなか透明のウレタンが見つけ難いことがあるんですけど、釣具屋だとよりどりみどりで逆に選ぶのに困ります。調達が終わったら早速修理開始です。
修理
まずはブランクスからガイドを取り外します。まずは第2ガイドをライターで軽く炙って取り外します。ちょっと炙るとすぐにトロッとウレタンが溶けるので、後はカッターで周りを削ると簡単にとれました。

折れた部分も綺麗な折れ口なので少し削れば良さそうです。
次にトップガイドを再利用する為に取り外す・・・が、これがうまくいかない。ブランクスが抜けません・・・うーん困った。ということで、いっそブランクスを燃やす事に。ブランクスというのはプラスチックと炭素繊維でできているので燃やすとぼろぼろになるはず。ということでペンチで挟んでライターで炙ります。おー燃える。少し冷ました後でブランクスを爪楊枝と針で穿り返すと綺麗に取れました。たぶん。

まあ穴の中に少し残ってるかもしれませんが、取りあえず装着に十分な深度は確保できたのでオッケー。素人の作業には多少の寛容な心が大事。
さてつぎは取り外したトップガイドを本体のブランクスに取り付けます。もちろん穂先の太さが違うので、そのままとりつけることはできません。参考にしたサイトによると折れたブランクスを削って本体のブランクスの穴に差し込んでいますが、今回はその穴がかなり小さく差し込むことができません。それ以前に燃やしちゃったしね。ということで、本体のブランクス自体を削って細くすることで差し込める様にします。カッターをつかってゴリゴリと削ります。結構硬い。あまり削りすぎると折れるので慎重に・・・おおよそトップガイドの穴の8割にはめ込めるようになったところで終了。

ちょっと危なっかしい状態ですが、このあと補強していけばどうにかなりそうな感じです。
さてこの状態でまずはブランクスの先にアロンアルファを塗ってトップガイドを取り付けます。この時のアロンアルファーは釣り用ではなく、プラスチック用を使用。これについては若干自信が無いんですが、ブランクスの成分はプラスチックを炭素繊維で強化したものと理解しているので、ガイドとブランクスの接地面自体はプラスチック用のアロンアルファについているポリマー(前処理剤)にて一度接着面を処理した方が強度が高いのではと考えました。ということで、ポリマーを綿棒で塗り塗りして少し時間をおきます。それからアロンアルファ本体で接着。あっというまに硬化。ちなみにこれはトップガイドだからって事もあって、中間のガイドだとブランクスに乗せてスレッド補修糸で接着するだけなので、曲がりに強いアロンアルファ釣り名人の方が良いんではないかと思います。
さて次はスレッド糸でブランクスとガイドを補強します。

巻き方はスレッド糸の商品自体に書いてある。

親切なパッケージでありがたい。補強の意味も込めてかなり広範囲に巻き巻き・・・3重に巻いて尖端を引っ張り込んで切断。

途中でちょっと巻き目が見えにくくなったので不格好になりましたが、強度的には問題ないということで続行。このスレッドを今度はアロンアルファ釣り名人で固めます。

こちらはスレッドとブランクス表面の伸縮を考慮して、柔らかい釣り名人を使用。巻いたスレッド全体に染み込ませて硬化させます。この時点でかなりの強度が出てきました。ここでさらにもう一手間。アロンアルファ釣り名人が乾いた上からウレタン系の硬化剤を塗ります。

2液式の硬化剤なので、一旦ペットボトルのキャップにストローで吸い上げて(口で吸うわけじゃ無いですよ。ズボッと漬けて反対の穴を親指で塞ぐだけ)2つの液を混合します。

若干硬化して粘土がでてきたところで綿棒で塗ります。あまり時間をおきすぎて、粘土が高くなりすぎると綿棒の糸くずがついてしまうので気をつけましょう。アロンアルファに比べると硬化速度はゆっくりなので焦らずにやれます。十分に塗ったら硬化を待ちます。半日は置いときましょう。
仕上げ

さて、ドキドキしながら曲げてみます。お~固まってる。曲げてもびくともしません。試しに天井へ・・・
きれいに曲がってます。表面にヒビもでてない。実釣してみないとわかりませんが、とりあえず成功の様です。さらにここで若干欲が。せっかくやりたい放題にできる竿なので、いっそ穂先を見やすいように色を付けてプチカスタマイズしてみることに。たまにルアーの着色に使っている蛍光オレンジのマニキュアでウレタンが硬化したところを塗ります。うーん、今思うとウレタンの前に塗ればよかった。まあ今さら遅いか。今度はそうしよう。。。ってな反省をしながら完成!

蛍光オレンジで穂先がぐっと見やすくなりました。再度天井での強度実験。

バッチリみたいです。
なんか夕マヅメアジとかメバル船とか乗りたくなっちゃう。そしたら更に蓄光塗料に塗り直したりしたくなっちゃったりして・・・。キャンプも釣りも新しいメンテナンスを覚えるのってたのしー!次はリールかなぁ。